理系ジェネラリスト
わたしたちがいま直面している問題の多くは、環境問題やエネルギー問題、少子高齢化問題など、従来の文系・理系という枠組では捉えきれない複雑な問題といえます。社会のさまざまな場面で生じるこのような複雑な問題に対して科学の立場から解決策を考え実行できる「理系ジェネラリスト」を育成して社会に送り出すことが創生科学科の目的です。

科学のみちすじ
授業では、文系・理系の枠を超え、「測る」「まとめる」「知る・伝える」ための理論と方法を体系的に学びます。これにより、科の立場から問題に挑む際の道標となる「科学のみちすじ」を身に付けます。
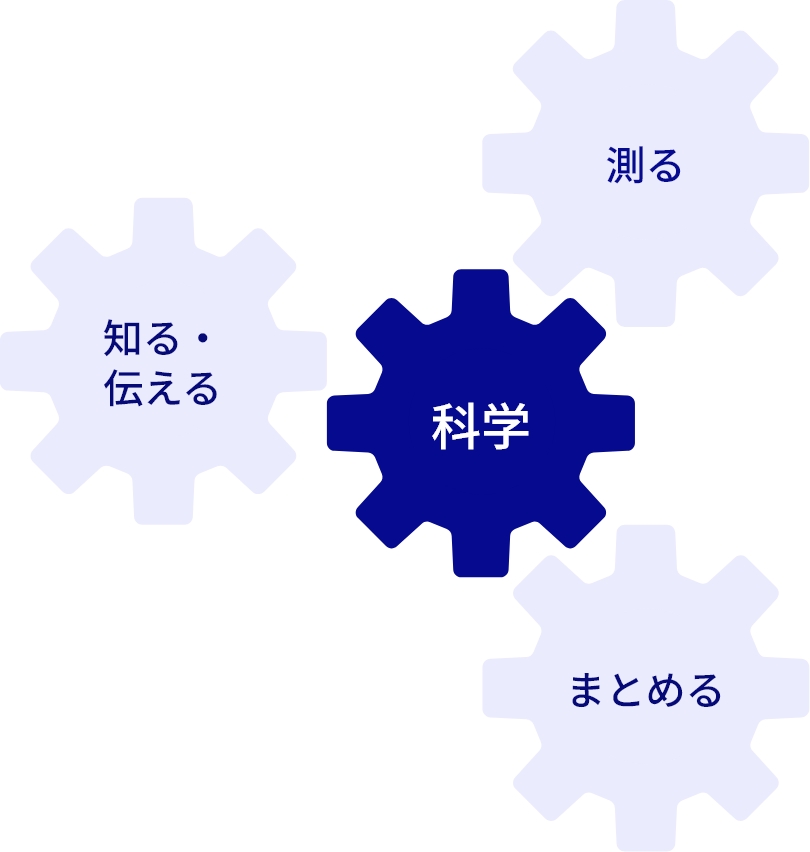
科学の創生に挑戦
3年生の秋から4年生にかけて、卒業研究として特定の分野の学問を深めます。自然現象や物質の性質を解明する「自然フィールド」、コミュニケーション能力を育成し、人間社会を理解する「人間フィールド」、人間の知能・知識をコンピューター上で再構築する「知能フィールド」で活躍する15名の担当教員とともに、それぞれの専門分野で科学の創生に挑戦します。

在校生・卒業生の声
在校生の声
-
2021年度入学
及川 千遥

 2021年度入学
2021年度入学及川 千遥
先端観測天文学研究室所属学部4年生
私の将来を決めた創生科学科での学び
- どんな研究に取り組んでいますか?
宇宙初期に似た環境を持つ星形成領域について研究しています。このような領域を調べることで、銀河がどのように誕生し進化してきたのかを知ることができます。研究対象の天体は銀河外縁部に属しており、今まで見つかってきた星形成領域と比べると、格段に暗く淡く見える点が特徴的です。従来知られている明るい星形成領域とどう異なるのかを調べることが私の研究の目的です。
- 大学生活の印象的な思い出は?
教職課程の履修が印象的です。法政大学の教職課程の授業はアクティブラーニングと呼ばれる、学習者が能動的に参加する授業形式が取られていることが多いです。この形式は学習者の主体性や課題解決力を育むことが出来るとされています。これを経験したことでより楽しく、深い理解に繋がっていると実感しました。また法政大学の教職課程センターは教員採用試験の対策も手厚く、教員を目指す方には非常に良い環境が整っていると感じます。
- 研究活動で得たものは?
天文学に関する知識はもちろん、データ解析を通じてプログラミングスキルが身に付きました。創生科学科ではプログラミング(Python)が必修授業です。当時はコードの意味が分からずプログラミングに対して苦手意識がありました。しかし研究には必須であるためデータ解析を進めるうちに慣れてきました。もちろん一人で解決できることばかりではないので教授に相談することも多々あります。プログラミングスキルだけではなく、自分の課題を整理して他者に相談し解決する力というのも研究を通じて培ったスキルの1つだと思います。
- 就職活動での強みは?
ロケットの軌道や衛星による測位システムには物理学や数学の基礎力が欠かせません。しかし宇宙開発の仕事はこういった能力だけではなく、世界規模で多くの機関と協力する必要があります。創生科学科では、俯瞰的に問題を解決しようとする力に加え、情報発信のためのコミュニケーションについてスキルを培うことができたと考えています。就職活動ではこうした学びを多くの人々との連携が不可欠な宇宙開発の仕事に生かせることがアピールできたと考えています。
- 今後の展望は?
天文学とは少し異なりますが、宇宙が好きという気持ちから宇宙開発を行う企業に就職予定です。そのため宇宙開発を通じて、宇宙というフィールドから地球の安全な暮らしに貢献したいと考えています。具体的には、近年増加する自然災害の被害を最小限にできる仕事がしたいと考えています。例えば「ひまわり」をはじめとする気象衛星は豪雨や大規模噴火といった国内外の災害場面で広く活用されています。授業や研究室活動での学びを生かして、こうした衛星の運用やそれを打ち上げるためのロケットに搭載するソフトウエアの開発に携わりたいと考えています。そしてこれらを通じて地球規模の課題に宇宙からアプローチしていきたいです。
-
2020年度入学
高森 悠平

 2020年度入学
2020年度入学高森 悠平
自律ロボット研究室所属学部4年生
ロボットが自ら安全かつ効率的に移動する仕組みを探求
- どんな研究に取り組んでいますか?
現在は自律移動ロボット研究室に所属し、ロボットが自ら周囲を認識しつつ安全かつ効率的に移動する仕組みを探求しています。障害物回避や経路計画、環境認識など幅広い分野であり、大変な場面が多々ありますが、研究室チームで実際に動かし、議論をしていくのはとても面白いです。
年二回、つくばとアメリカである大会での完全走破という目標もあり、充実した研究だと思います。
- 大学生活の印象的な思い出は?
それはもちろん留学です。
元々アメリカの雰囲気が大好きでしたので留学は何年も前から決めていました。
リスニングがやはり最難関でしたが、慣れるといけるもんですね笑
友人とパーティー、旅行、ドライブ、授業プレゼン、特にアメリカならではの交友関係が言葉に出せないくらい幸せでした。
異国の地という怖さもなく、ずっと夢の国にいたような一年でした。
- 研究活動で得たものは?
主に問題解決能力です。
ハード・ソフトどちらも不具合が発生することがあり、
それについて仮定を挙げつつ論理的に解決していく能力が身についたと思います。
その過程で、チームでの協力・議論を通じたコミュニケーション能力の成長も感じています。
- 就職活動での強みは?
院進学予定のため、現時点では解答できません。
- 今後の展望は?
同じ研究室で大学院に進学予定です。
学部時代の研究を通じてより自律移動ロボットの研究に携わりたいと思いました。
また社会に出た際、必要な人材になるべく大学院進学は必須だと改めて感じました。
-
2021年度入学
鈴木 ひかり

 2021年度入学
2021年度入学鈴木 ひかり
応用言語学研究室所属学部4年生
なりたい自分が見つかる~学び、夢、発見を創生(ここ)で~
- どんな研究に取り組んでいますか?
応用言語学ゼミに所属し、日本全国にある大学校歌の歌詞の計量テキスト分析に取り組んでいます。校歌をテキストデータ化し、テキスト分析ソフトにかけることで、地域ごとに特徴は見られるのか、国立・公立・私立大学の校歌で違いはあるのか、戦前と戦後に作られた曲で差はあるのか等を調べる研究です。個人的に驚いたことは、国立大学の校歌に頻出する名詞は、公立・私立大学校歌に頻出する名詞と少し違いが見られたことです。今後も考察を深めていきたいです。
- 大学生活の印象的な思い出は?
大学合唱団での活動です。合唱では母音や子音の発音や発声方法、倍音などの「音声学」の知識が必要となります。合唱で習ったそれらの知識が、所属している応用言語学ゼミでの学習に活かせた場面がありました。また、法政大学の3キャンパス合同の合唱団で仲良くなった地理学科の友人から学問としての歌や地理学の楽しさを教わり、自分の卒論のテーマを決める上でヒントを沢山もらえたことが印象に残っています。
- 研究活動で得たものは?
問題に対して仮説を立て、実験・分析によって考察するプロセスが身に付きました。例えば、アンケート調査から平均値や最頻値を算出し、定量的に考察するだけでなく、少数派の回答にはどのような意見があるのかを質的に分析・考察する力です。これらのプロセスをレポートや論文にまとめていくことで、自分の中で論理的思考力が成長したと思います。
- 就職活動での強みは?
幅広い学問を学べるため、進路の選択肢を広げられるところだと思います。例えば、実験での回路設計やデバイス、プログラミングを扱った経験を活かしてエンジニアになる、数学を活かしてアクチュアリーやQCになる、教員になるなど、多様な可能性があります。事務や営業職においても、科学に触れてきたバックグラウンドがあることで活躍できるフィールドが十分あると思います。
- 今後の展望は?
家電メーカーに就職し、大阪でQC(品質管理)として働く予定です。QCを選んだ理由は、授業で学んだ統計数学に興味を持ち、その学習が活かせる職種に就きたかったからです。また、私は東京生まれ東京育ちですが、昔から関西のグループや関西弁に憧れがあったため勤務地は大阪を希望しました。何もかもが初めての環境に期待と不安でいっぱいですが、どんな壁もポジティブに乗り越えていきたいです。
卒業生の声
-
2022年度卒業
村田 夏樹
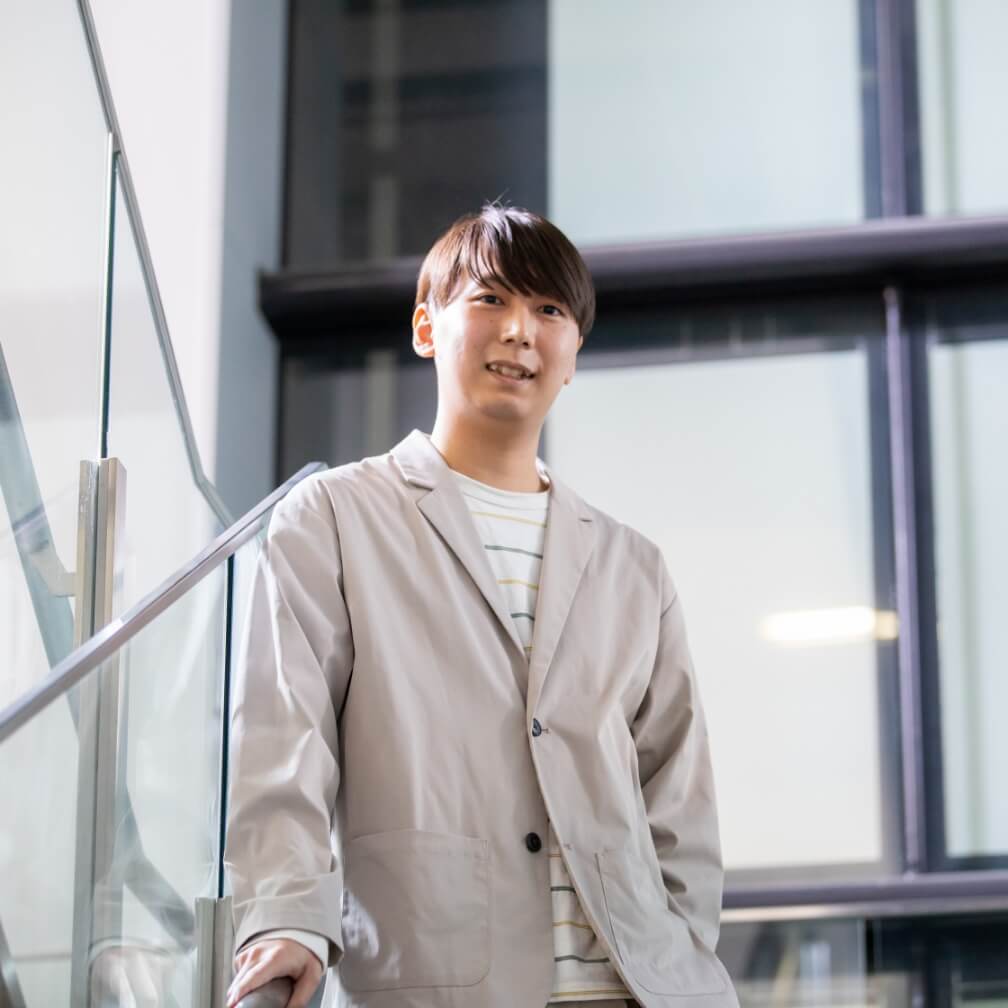
 2022年度卒業
2022年度卒業村田 夏樹
人工知能・機械学習研究室所属修士2年生
高校生の頃の私へ 私はこの道を進みます
- 大学院に進学した理由は?
大学院に進学した理由は、研究を通じて人工知能の可能性をもっと深く追求したいと考えたからです。創生科学科では、理系科目だけでなく、文系や教職科目も学ぶことで広い視野を持つことができました。特に所属する「人工知能・機械学習研究室」では、自然言語処理や画像認識など、各自がテーマを決めて研究します。大学院では、自分の研究が社会の中でどのように役立つかをさらに考え、発展させていきたいと思っています。
- どんな研究に取り組んでいますか?
私が取り組んでいる研究は、「大規模言語モデル(LLM)」を使って数学の問題を解く方法を探るものです。LLMは、人間の言葉(日本語や英語など)をコンピューターが理解し、処理する技術です。具体的には、LLMが出した答えが正しいかどうかを別のLLMで判定し、不正解の場合はその理由を追加して再チャレンジさせる仕組みを研究しています。この方法で、モデルの精度をさらに向上させることを目指しています。
- 今後の展望は?
大学院修了後は、人工知能の知識を活かしてエンジニアとして活躍したいと考えています。研究で学んだことをもとに、新しい技術を提案したり、業務を効率化する仕組みを作ったりすることが目標です。その後、10年ほど実務経験を積んだ後は教員になりたいと思っています。企業での経験を活かし、生徒たちに「学ぶことの大切さ」や「社会での生き方」を伝えられるような教員を目指しています。
- 入学を目指す学生にメッセージを!
私も高校生の頃は「理系の勉強をしてみたい」くらいの気持ちで大学を探していました。創生科学科は、さまざまな学問に挑戦できるだけでなく、多様な仲間と刺激を受けながら学べる学科です。この環境で私は、幅広い学問の基礎と人工知能の専門知識を学ぶことができました。進路に悩むこともあると思いますが、自分の選択に自信を持てるよう、最後までしっかり考えてみてください。