
金沢 誠
Makoto Kanazawa応用論理・数理言語学研究室 — 証明プログラミング
近年、100%証明を信頼するためには、証明をコンピューターを使ってチェックするべきであるという考えが広がりつつあり、静かな革命が起きています。コンピューターがチェックできるような形式で詳細に証明を書き下すことを証明の「形式化」と言います。研究室では、主にプログラム検証(プログラムが正しく動作することの証明)の形式化に取り組んでいます。

金沢 誠
Makoto Kanazawa近年、100%証明を信頼するためには、証明をコンピューターを使ってチェックするべきであるという考えが広がりつつあり、静かな革命が起きています。コンピューターがチェックできるような形式で詳細に証明を書き下すことを証明の「形式化」と言います。研究室では、主にプログラム検証(プログラムが正しく動作することの証明)の形式化に取り組んでいます。

小林 一行
Kazuyuki Kobayashi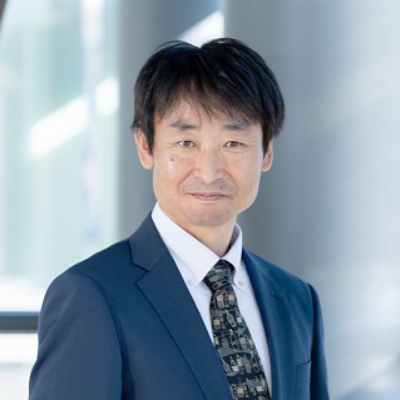
小宮山 裕
Yutaka Komiyama―― 私たちの住む宇宙はどのように生まれ育ってきたのでしょう? ――この問いに、最新の望遠鏡やユニークな観測装置を使い、銀河や星といった天体の観測を通して答えを見つけていくことが、当研究室で行っている観測天文学です。ただ観測をして得られたデータを解析するだけではなく、新たな観測計画を企画・検討したり、先端技術を取り入れた観測用カメラを作ったり、多角的に研究を進めています。

小屋 多恵子
Taeko Koyaことばとそれを使用する人間 (教育, 社会, 文化等) に関わる研究をやっています。興味のあるテーマを設定し、アンケートやデータベースから、量的・質的に分析し、傾向、特徴や法則を見つけていきます。例えば、英語コーパスを利用し、ジャンルごとに特徴的なコロケーション(語と語の相性)、語法、論理展開を分析する、学習過程においてどのようにやる気が変化するのか?、声のかけ方によりやる気の変化は?を調査する、映画の台詞の英語版と日本語版を比較する等、さまざまです。

松尾 由賀利
Yukari Matsuo物質の根源である、原子・分子、原子核の研究をしています。なかでも、レーザー分光により原子や原子核などの情報を探ったり、レーザーアブレーション法といって、レーザーの強いパワーを瞬間的に極めて狭い領域に絞り込むことで物を切ったり削ったりして、ミクロな物質を詳しく調べる実験に力を入れています。

佐藤 修一
Shuichi Sato重力波をキーワードとして宇宙天文・精密計測・衛星開発の分野に研究を展開しています。宇宙天文の研究ではわれわれの住むこの果てしなく広い世界の「時間」と「空間」はどのように一点宇宙から誕生したのか?を重力波で解き明かします。精密計測の研究では10のマイナス25乗という想像を絶するような極微小量の計測に最先端技術を駆使して挑みます。衛星開発の研究では革新的技術を衛星に搭載して今まで見たこともないような宇宙の観測に挑戦します。

柴田 千尋
Chihiro Shibata深層学習(ディープラーニング)を中心とした機械学習の基礎研究と、学際的な応用研究を行っています。基礎研究としては、深層学習・機械学習アルゴリズムの理論的基盤を研究しています。例えば、ニューラルネットワーク内部の埋め込み表現を利用した、解釈(いわゆる説明可能性)についての研究などを行っています。応用研究としては、深層学習を用いて、実世界の諸問題に取り組んでいます。具体的には、質問応答や文生成、感情分析などの自然言語処理、医療データ分析、画像認識、画像生成、異常検知などを研究の対象としています。特に、大学病院などの他の研究機関との共同研究を含め、異分野との接点を通じて、自由で多彩な視点から、新しい研究成果を創り出すことを目指しています。
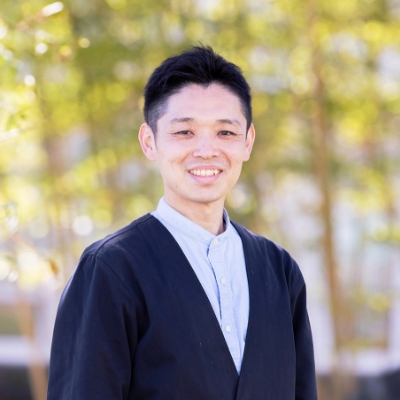
鮏川 矩義
Noriyoshi Sukegawaデータから最適解を見つける方法を研究しています。たとえば、「どのような経路でゴミを回収すれば作業時間が短縮できるか」、「どのような席替えをすれば生徒からの不満が減るか」、「どのような試合日程表なら各チームにとって公平か」といった疑問に答えることが目的です。数学とコンピュータをどのように活用するかが研究の鍵となります。

鈴木 郁
Kaoru SuzukiAIを含むソフトウェア、電子回路などのハードウェア、そしてそれらの組み合わせで、高齢化などヒトに関わる問題の解決を目指します。具体的には、「騒音感応型音声加工処理」、「段差警告機能を有する白杖」、「距離測定画像を用いた個人識別」、「初心者向けランニングフォーム・フィードバックデバイス」などに取り組んでいます。

田中 幹人
Mikito Tanaka「宇宙をパーソナルイノベーションする」をミッションに掲げ、天文学に、音楽、教育、IT、観光など他分野を掛け合わせることで新しい宇宙文化の創出に取り組んでいます。また、宇宙文化は良質な星空環境の下で生まれることから、その自然環境を保護していくために、日本で最も美しい星空を有する福岡県八女市星野村を実践フィールドとし、星と文化の持続可能なまちづくりにも取り組んでいます。

堤 瑛美子
Emiko Tsutsumi学校で授業を受けている時、自分で勉強をしている時に「理解が追いつかない」「どこから勉強すれば良いのかわからない」「そもそも何が分かっていないのか分からない」と感じた経験がある人は多いでしょう。自分で完璧な学習計画を立てて実行することはとても難しいことです。かといって先生が生徒一人一人に合った指導をすることにも難しい課題があります。教育工学研究室では、過去の生徒の学習履歴データを分析し、個人に最適な学習計画を提案する技術を開発しています。

呉 暁林
Xiaolin WUインターネットの普及やPC・スマホなどの機能の向上により、企業と商品の情報、消費者の口コミや好き嫌いなどの評価、沢山の情報が容易に収集できるようになりました。私達の研究室では、インターネット上に公開された膨大な量のデータを収集・分析することにより、さまざまな市場における企業のポジショニングや商品のターゲット層、消費者の選択行動、市場ニーズなどを分析し、社会経済やマーケットにおける課題の解決に挑戦しています。また、ChatGPTやDeepSeekなどを活用する効率的な語学学習と多様な社会的実践にも取り組んでいます。

山本 晃輔
Kohsuke Yamamoto「どうして勉強しても覚えられないことがあるの?」や「匂いを嗅ぐと昔の記憶がよみがえるのはなぜ?」といった、みなさんが日常で感じる不思議な現象を、実験や調査を通して解き明かしています。また、高齢化が進む社会で、高齢者の記憶力を保ったり、ウェルビーイングを支えたりするための研究にも取り組んでいます。
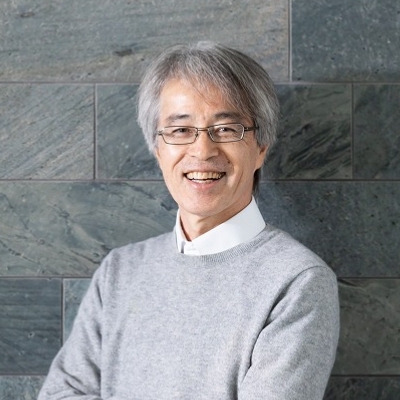
柳川 浩三
Kozo Yanagawa中学・高校の先生になりたい人を全力で応援します。当研究室では、多様な教育・社会問題の中からあなたがオリジナルな「問い」を見つけ、データサイエンスの知識とスキルを駆使してその問いに対する解を見出すプロセスを通じ、あなたの想像力・思考力・表現力・データ分析力を鍛えます。それによって、あなたが教員として自立してやっていける自信と素地を養います。

横山 泰子
Yasuko Yokoyama機械化や情報化によって、人間社会が劇的に変わっている今、「人間」とは何かが問われています。人間とは何かを考えるために、「人間ではない何か」からスタートすることが有効ではないかと考え、妖怪の研究をしています。日本ではカッパや天狗など、様々な妖怪のイメージが流通していますが、彼らは人間とどう違うのでしょうか。また、私達は生きている人間の中で生きていますが、死者が登場する幽霊の物語はなぜ作られるのでしょうか。日本の妖怪文化を研究することで、人間とは何かを考えるのは「怖い」一方、「楽しい」ですよ。